乙女心に満たない初々しさ

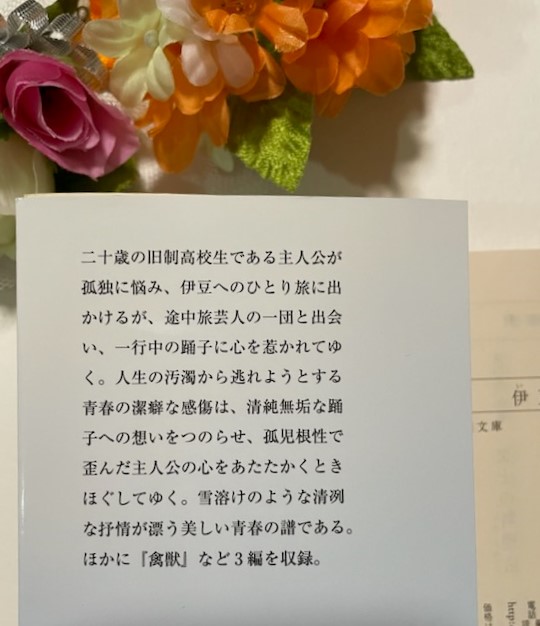
主人公と踊子のただただピュアなやりとり。
すでに何回か顔を合わせている状態から物語は始まり、一緒に旅をする中での2人のやり取り、取り巻く人々の人物像が描かれている。
主人公は20歳とあって、世間慣れはしているが、性には敏感で初々しさを感じる。
踊子は14歳、化粧で大人びて見えるが、異性を意識し始めたばかりの無垢さ。
旅芸人や女性への差別、富や教育の格差、人間社会の汚い描写の中で
2人のこのアンバランスさが綺麗に映る。
私が気になった描写
突っ立っている私を見た踊子が直ぐに自分の座布団を外して、裏返しに傍へ置いた。
新潮文庫版P8から引用
前の人の熱が残っていたら嫌だろう、という気遣いだそう。寄席に限ったマナー、埃が立つから失礼といった意見、習慣の違いもあるようなので一概に正しいとは言えないようです。
髪を豊かに誇張して描いた、稗史的な娘の絵姿のような感じだった。
新潮文庫版P9から引用
主人公が踊子の様子を表現した部分。稗史的(はいしてき)と読む。民間に伝わる話やそれらに基づいて編集された史書。うーん、意味が分かっても踊子の様子が想像できるかというと・・・。
好奇心もなく、軽蔑も含まない、彼等が旅芸人という種類の人間であることを忘れてしまったような、私の尋常な好意は、彼等の胸にも沁み込んで行くらしかった。
新潮文庫版P31から引用
この文脈での尋常は、”特別でなく、普通であること”の意味で使われていると思われる。
今はあまり使わない表現ですね。
船で去る主人公に向かって踊子が振った”白いもの”とは何か
ずっと遠ざかってから踊子が白いものを振り始めた。
新潮文庫版P44から引用
別れの朝、主人公を見送りに来た踊子は「さよなら」も何も言わず、ただ黙っている。きっと閉じた唇、主人公の話にただうなずくだけ。寂しさ、憤り、、、踊子はまだうまく感情表現ができない、そのくらい子供であり純粋なのだ。
遠ざかる船に向かって踊子が振った白いもの。これに関してはネット上でも論争がある。
ハンカチか手ぬぐいか論争。
一度、踊子がハンカチで主人公の足元を拭いてあげたという描写があるので、ハンカチだったのではないかと私は思いますが。
でもどっちでも良いと思います。
私がこの描写から感じたのは、踊子=”白いもの”。
主人公の願望なのか、川端康成自身の願望なのか、
私は涙を出委せにしていた。頭が澄んだ水になってしまっていて、それがぽろぽろ零れ、その後には何も残らないような甘い快さだった。
新潮文庫版P45,ラストから引用
最後まで踊子をきれいな思い出として描こうとした、そう感じました。
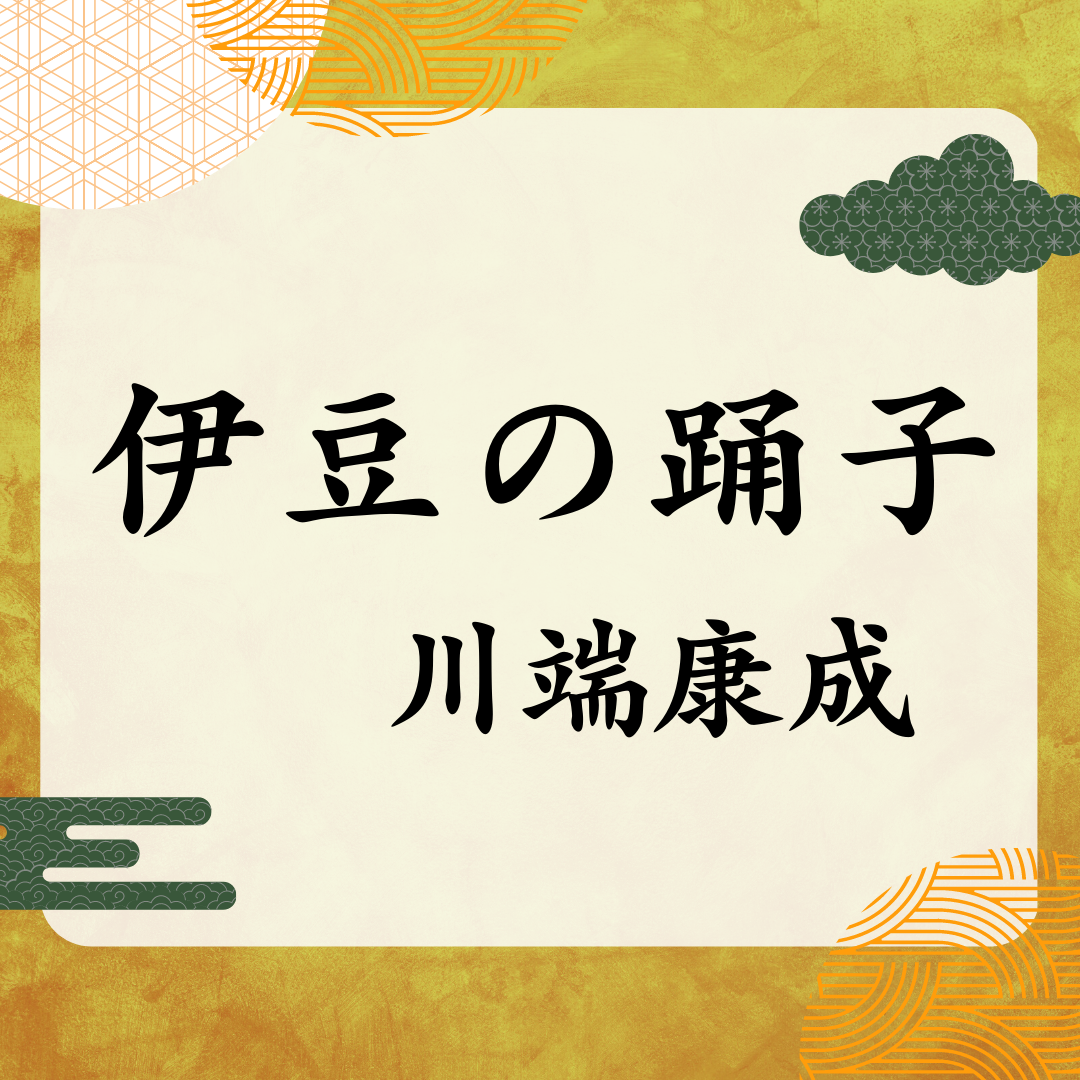
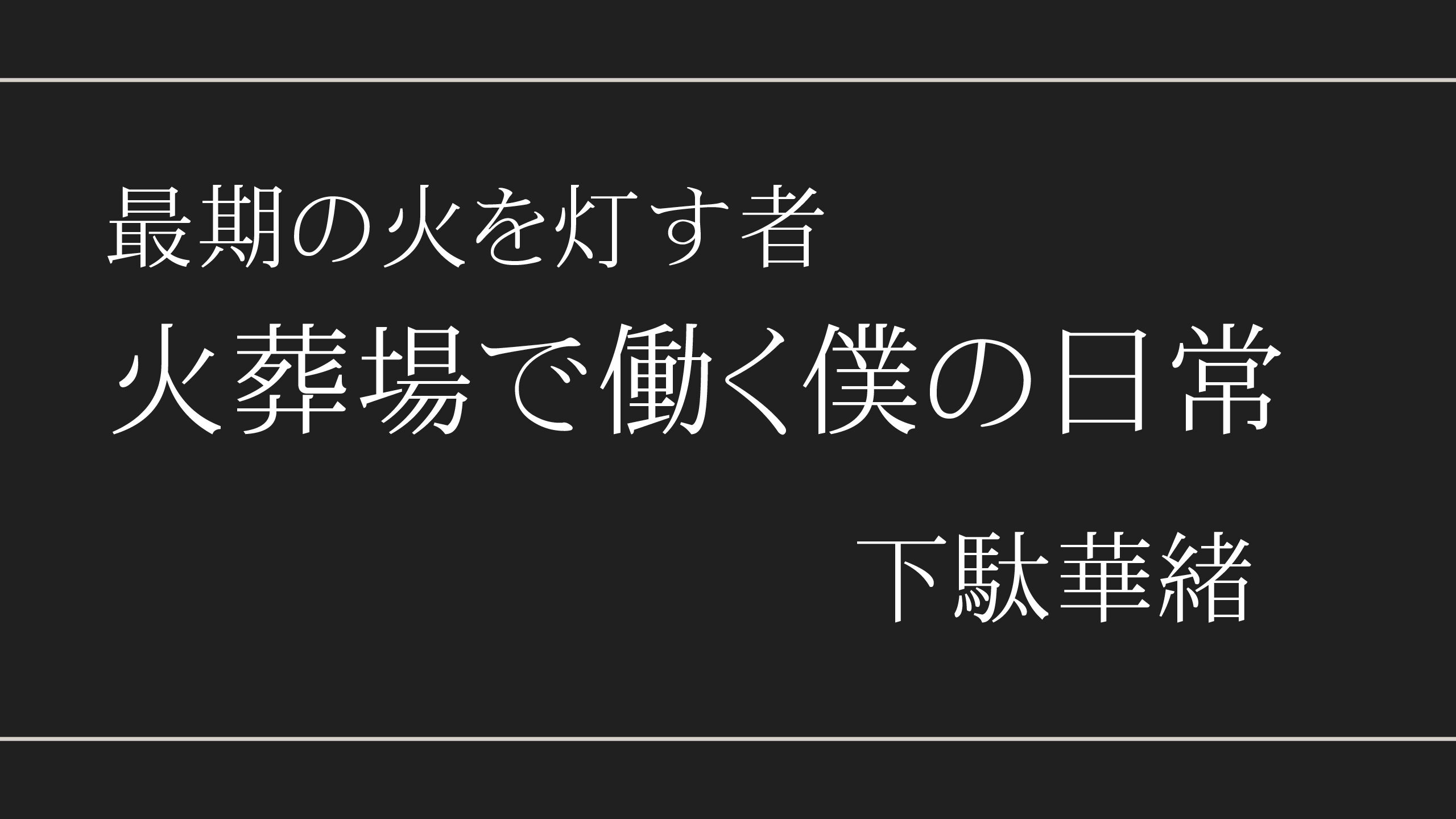

コメント